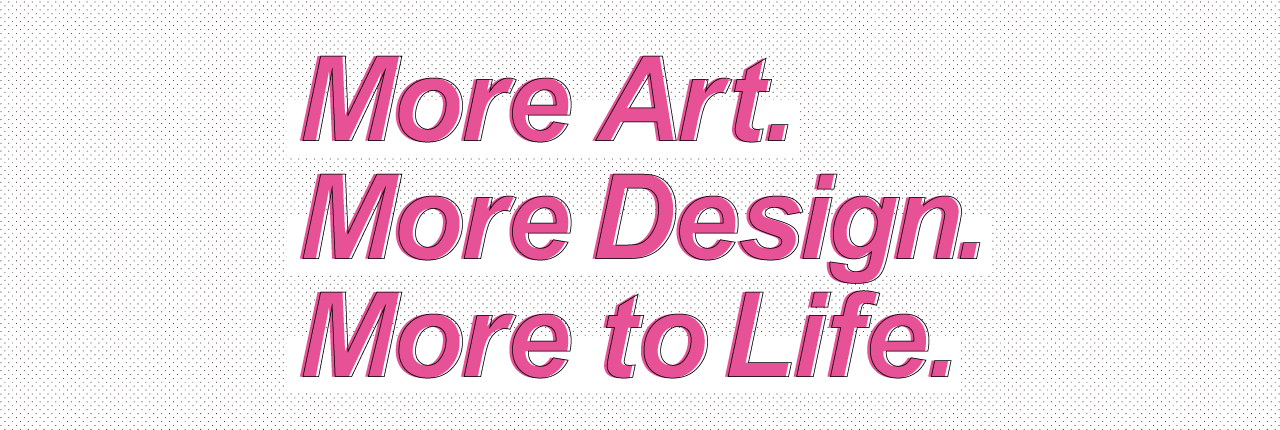学長からのメッセージ

この世界にも、
あなたの人生にも、
もっと「アート&デザイン」を。
あなたらしい未来を切り拓くため、
新たに進化する芸工大で、
その一歩を踏み出そう。
東北芸術工科大学学長
中山ダイスケ
アートとデザインを学ぶということ
More Art. More Design. More to Life.
本冊子のこのテーマは、「この社会には、もっとアートやデザインが必要だ」という本学の考え方のもと、「アートやデザインを学ぶことで、あなた自身を成長させ、人生を豊かにしよう」という、新入生への提言です。
パンデミックや各地での戦争、気候変動、人間の心の病、まるで地球全体が病に侵されているかのようです。そんな今だからこそ、アート&デザインの柔軟な思考が、世界で強く求められていると感じています。これまでみんなが信じていた経済力や科学技術力、政治力や軍事力に頼りきっていたら、見事にこんなに荒れた世界になってしまいました。大きな力や、ほかの誰かに頼っているだけでは、もう誰も幸せにはなれません。世界には、クリエイティブなアイデアが足りていないのです。
これからも世界は変化を続けます。新たな災いや争い、価値観の転換、国境や政治体制だって変わることがあるかもしれません。そうやって何か変化が訪れるたびに、これまでの「あたりまえ」が崩されていく。だからこそ、何が起こっても、そこから新しい考えを生み出せるクリエイティブ力が必要なのです。これまでの正しい答えを疑い、別の答え「別解」を導き出せるような柔らかさを身に付けてもらうための学問、それが「アート&デザイン」です。
東北芸工大は、新しいアート&デザインを学べるだけではなく、活用を試せる貴重な場所です。その大きな理由は、本学が山形という地方都市にあるからです。山形は、単なる大自然に囲まれた美しい東北という側面だけでなく、少子高齢化、人口減少、働き手不足など、多くの社会課題に直面した「課題先進県」です。山形はこの先、日本全体が必ず直面することとなる重要な社会課題に、全国よりも10年ほど早く向き合っています。言わば山形は「最先端の地」であり、「未来の日本の姿」なのです。


新分野6コースを含む、
12学科・コースがあたらしく
本学はそんな時代のニーズに備え、アート&デザイン分野のさまざまな学科・コースを揃えていますが、2026年春からこれまでの学科編成に、6つの新分野を加え、学びの領域を全 19 学科・コースに広げます。
まず、映像学科には、新たに「キャラクター・ゲームコース」「CG・アニメーションコース」を新設します。すでに日本のアニメやゲーム開発力は世界から注目されていますが、ますますデジタル化され、精鋭化されていく最新の表現技術を集中的に学べるよう、専門性を特化し、世界の映像制作の現場をリードできる人材を育てます。
アート分野では、高度な版画やプリント技術を基礎に、アート表現や社会へのメッセージとしてのグラフィック&アートを学べる「グラフィックアーツコース」を新設。デザイン分野にも、情報の伝達手法としてのイラストレーション技術を学ぶ「イラストレーションコース」を新設しました。今後一層高まるグローバル化のなか、アートとデザインの両学部から、世界中の人々が言語の壁を超えて視覚で理解し合える、新たなイラストレーション活用の可能性に挑みます。
さらに、新設される「彫刻・キャラクター造形コース」は、これまで美術の一分野として存在していた、鑑賞のための「彫刻」の枠組みを超えて、もっと人々の生活に近い造形作品やオブジェ、立体のキャラクターデザインにまで範囲を広げ、街や社会を楽しく彩る新しい立体作品の世界を創ります。
そして、企画構想学科には、国内の芸術系学部では初の「食」の分野、「食文化デザインコース」を新設します。「日本食」は、すでに世界に認められたアートでありデザインですが、身近なテレビやネットの中にも、食のエンタメ、調理バラエティーなど、さまざまな食の表現が溢れ、広く愛されている重要なコンテンツです。さらには、世界中の地域に伝わる食文化や特産品の研究、食糧不足や生産者不足、輸出入される食材、食や水の安全、ファストフードと健康問題、フードテックと呼ばれる最新技術など、学ぶべきテーマに満ち溢れています。農業王国であり、食材の宝庫と言われる山形地域の強みを存分に生かし、食とデザインを専門に学んで新たな食文化をリードできる未来人材の育成に挑みます。
19学科・コースに及ぶ本学独自の学科・コース編成は、新たな人材を迎えながら、常に連携し合っています。例えば、絵を描かないデザイン学科「企画構想学科」には、「社会学系に進もうと思っていた人」や「街づくりをしたい人」のような、これまでは一般大学に進んでいた学生が入学し、デザイン的手法を学び、映像やグラフィック、プロダクトの学生と共同開発をしています。さらには、建築とアート、グラフィックと文芸、映像と歴史がコラボしたりと、「コト」のデザインと「モノ」のデザイン、そこに芸術表現が組み合わされた、プロと同じ「仕事の現場」が、学内に自然に生まれています。将来は起業したいという学生が増えているのも本学ならではの特徴でしょう。


東北芸工大だから提供できる、
出会いと成長の場
こうした専門分野を横断するコラボが可能なのは、本学の専任教員が現役で活躍しているクリエイターばかりだからです。現役を引退されたクリエイターの「昔話」ではなく、今を生きるクリエイターの「現実」を伝えなければ、本学が目指す最新のクリエイティブ教育は実現できません。
本学では、現役のプロである教員たちが、自身のプロジェクトや外部からの研究依頼を、学生の教育に活用できるようにプログラムをデザインし、多くの現役クリエイターを専任教員として集めることに成功しています。生き生きとしたクリエイター教員から、制作現場での日々の喜びや苦悩を直接教われるというのは、東北芸工大だけが実現できた魅力の一つです。
本学が地域から依頼される案件は、年間100件を超えています。東北芸工大の演習の大部分はリアルな課題です。「クリエイティブをどう社会に活用すべきなのか」という課題を、実社会との関わりの中から学んでいくので、社会との対話力に長けた柔軟な学生が自然に育ちます。
芸術大学に進学する人は、幼い頃から「創作が好きな人」「才能やセンスがある人」、というのはもう昭和時代の話です。皆さんの保護者の中にも「アートやデザインでは食べていけない」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、今やアートもデザインもゼロから学ぶことのできる「学問」であり「教養」、そしてさまざまな「職業」の入り口です。4年間をプロと共に学んだ東北芸工大生の就職率は、全国の芸術大学でトップクラスです。毎年、学生数の約20倍にのぼる求人をいただいています。東北芸工大は、日々の学びを進路に結び付け、「就職できる芸術大学」なのです。社会人になってアート&デザインを生かした仕事に就きたい、プロになりたいと思うのであれば、本学はその近道です。

あなたらしい未来を切り拓く場所、
東北芸工大
東北芸工大は他の芸術大学とは全く違いますから、できるだけ来て、見て、教員と話して、自分の目で選んでほしい。他大学のオープンキャンパスともよく見比べてみてください。そしてもし、あなたの未来イメージが東北芸工大と重なったならば、ぜひ我々クリエイターチームの一員になってください。
「好きなこと」をやりたい人はもちろん、「美しさを追求したい」「世界を変えたい」人も、「どうして社会はこんなに不平等なのか」「つまらない社会を変えたい」と、世の中にフラストレーションが溜まっている人も、それぞれのいろんな力をここに集めたいのです。
More Art. More Design. More to Life. 私たちと世界を変えましょう。


なかやま・だいすけ/アーティスト、アートディレクター。アート分野ではコミュニケーションを主題に多様なインスタレーション作品を発表。1997年よりロックフェラー財団、文化庁などの奨学生として6年間、NYを拠点に活動。1998年第一回岡本太郎記念現代芸術大賞準大賞など受賞多数。1998年台北、2000年光州、リヨン(フランス)ビエンナーレの日本代表。デザイン分野では、舞台美術、ファッションショー、店舗や空間、商品や地域のプロジェクトデザイン、コンセプト提案などを手掛ける。2007年より本学グラフィックデザイン学科教授、デザイン工学部長を経て、2018年より東北芸術工科大学学長。