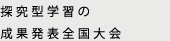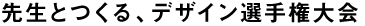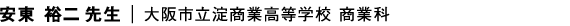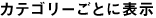時間、対象人数
2、3年生の自由選択科目の授業(2年:マーケティングデザイン〈2単位〉、3年:商業デザイン演習〈2単位〉)のなかで、夏休みの課題としてデザセンを位置づけています。
対象人数は、毎年希望によって異なりますが、40名前後といったところでしょうか。ただ困ったことに、生徒がこの授業を選択する動機づけとしてデザセンは全く意識されていないのが難点なんです(笑)。一応シラバスには明記しているのですが…(悲)
「PCを使えるようになりたい!」「カタカナの授業名がかっこよかったから…」「授業名のデザインの響きが気に入ったから…」などという生徒が大半を占めています。
こんな感じの船出ですから、デザイン、PCの素人・商業科集団をいかに引っ張っていくかで四苦八苦しているのが現状で、いつもゼロからの出発です。
理由、目的、達成目標
「自分自身で新しい情報を創造する能力を養うために。
…デザセンはもってこいの大会」
・受身的情報記憶から自発的情報創造を目指して
私は、いまや情報を記憶する価値よりも、いかに適格に必要な情報を探索し、組み合わせ、新しく表現できるかという創造能力の方が重要視される時代であると感じています。アクセスできる情報量は記憶能力をはるかに超えているからです。これからは、自分自身で新しい情報を創造する能力が問われてくるに違いありません。そこで、デザセンはもってこいの大会、学習の機会だと捉えています。
デザセンの目標は、学習者が自発的に学習することが前提になってきます。生徒は受動的な授業形態に慣れてしまっているので、自発的、積極的行動への頭の切り替えが必要になってきます。思い切って情報を厳選し、どのように対象に迫っていくかという学びの方法、学び方に関わる知識や技術の習得を目的に取り組ませています。
・情報吸収からプレゼンテーション力育成へ
プレゼンテーションを通して、私たちの触れる情報は改めて加工されたものであると認識するとともに、その認識はあふれる情報に対して批判力を養うことに繋がると思います。また、発表することを通して人との交流が生まれ、新たな出会いへと展開されていくことを楽しんでほしいと願っています。発表するということは、常に第三者的な視点が生徒の心のなかに存在することになり、客観的なものの見方ができるようになってくるでしょう。ひいては自分の立場からだけでモノを考えるのではなく、他人の立場からも、モノを考える力を養うという今の生徒に欠けがちな大切な能力を育てることにも通じてくると考えています。
そして、インターネット時代においてはその情報を発信する力、自分の主張が世界に伝わる!という実感が、生徒の個性を伸ばしていくものだと考えています。

『ハンコサプリメント』 デザセン2008 第15回大会 入賞
指導方法
1. Planning
「意識付け」「チーム編成方法」
まず、最初の授業は過去のデザセンDVD鑑賞大会。一応に「スゲェー」「私たちには無理!」「この授業をとって失敗した…」という歓声。次に、募集要項のデザセンサイト検索。そこで、賞金額を見るやいなや…早くも獲得したときの使い道など…やる気の歓声(笑)。
チーム編成は、座席の順番通りで強制的にこちらが決めています。「自由にしたい!」という不服のある生徒には、さらにもうひとつ別チームにおいてエントリーするのはOKだよと伝えます。しかし、まだ誰もそういったチームでエントリーしてきた生徒はいません…。そこまではしないんですよね…。
「問題課題の発見(テーマの設定)」
過去のデザセンのテーマ分類を見てみると、「国際理解」「情報」「環境」「福祉」「健康」といった様々なテーマが挙げられています。これらを具体化するときに、私なりのヒントとして一言で述べるなら『生徒にとって身近でかつ大人ですら未解決な問題に、生徒の新しい視点で挑めるテーマ』を選べばいいと考えています。
私たち教師は明確な解答がないという不安から「大人ですら解決されていない問題を生徒には無理だろう」と考えがちですが、他の教科と違ってこの学習は、既にある知識を暗記させる学習ではありません。現実問題に触れ、いかにして変化する社会に立ち向かうかを身に付けるためであり、対応の方法を学ぶことが主眼となります。
しかし、実際には研究に伴い、新しい知識が獲得されるのは確かであり、知識学習を否定するものではありません。そのために、教師にも勉強が必要になってくるのは当然のことなんですが…。私は苦しんでいます…我苦愁(苦笑)。
2. Produce
「アイデアの拡散、収束」
ポイントとして挙げるなら、私は次の3点を重要視しています。
(ⅰ)データに基づく客観的な考え方による仮説の検証・提案
(ⅱ)実感(体験)重視
(ⅲ)新しい視点
(ⅰ)データに基づく客観的な考え方による仮説の検証・提案
集めたデータの加工作業、そしてどのように分析するかということは、その後の成果の出来、不出来に大きく関与してくるものと思われます。客観的な考え方により仮説検証しておかなければ後で必ず混乱が生じてきます。生徒は短絡的に仮説を立てがちなので、教師はこの点を十分注意する必要があると思われます。生徒の稚拙な提案を、ときにはバッサリと切り捨てながらも、「いや、アリだよな…アルかもな…」という感覚も同時に忘れないように心がけています。
(ⅱ)体験重視
生徒を放っておくと、インターネット等の情報をそのまま収集・加工に終始しがちになります。私は、必ず"実感できる「体験」"を重視しなければならないと考えています。本当はこれが一番重要ではないかと考えるほどです。バーチャル体験では駄目なのです。ただ単に、インターネットなどで資料を集め、まとめて、コンピュータを使って発表するといった、体験や行動が伴わない研究は総合学習とはいえないと思いマス。
現実社会を肌で感じ取る「情報」その"感性、感動"こそが「生きる力」に変わっていくものだと思うからです。この「行動、体験」を通して得られる貴重な精神を抜きにして、「情報活用能力の育成」などを進めていくと、バーチャル感覚は磨かれていくでしょうが、現実社会との距離が妙にズレてしまい、危険な方向に行ってしまうような気がします。
(ⅲ)新しい視点
最後に、難しい現代社会の問題をどう切り開いていくかというときに切り札になってくるのが"新しい視点"ということになると思います。幾つかアイデアを披露してみると、こんなモノはいかがでしょうか。
例えば、「常識を疑ってみるといった視点」、「若い女性の立場でモノを見直すといった視点」、「個人(ローカル)の視点とグローバルな視点の比較」、「男と女、大人と子どもの視点の比較」、「ハイテクとローテク、開発と破壊の両面からのアプローチを試みる」など、こういったファクター、言わば切り口からアイデアを拡散していきます。
『日本語のこころを学びマス!』 デザセン2010 第17回大会 入賞
3. Presentation
「発表(報告 提案)」「新たな問題点の提起」
例えば、2010年のデザセンでは、最近の若者言葉の乱れに着眼し「本当に日本語の意味を理解しているか?そして、美しい日本語のこころを復活させよう!」をテーマに決定。最近の意味不明な若者言葉を調査、データ収集を行う。自分たちなりに学びながら覚えられるように言葉に関するちょっとした疑問が調べられる。そして日本語の本当の意味を楽しみながら覚えられるよう携帯電話と連携したゲームがつくれないか。さらに、日本語の美しさも理解できるようにと古くからある「すごろく」と結び付けて提案しました。
取り組みによって得られるもの …今後の課題、抱負
1. 生徒感想文より抜粋
・この数ヶ月のことは、卒業しても絶対忘れられない …A.T
・みんなでひとつのことを作り上げていく楽しさ、難しさを知った …M.H
・たぶん一生できひんコトやと思うからスゴイ経験ができたと思う …M.O
・自分にもできるという自信と勇気が付いた。
きっとこの経験を通して人間的に成長したと思う …O.M
・チームワークの大切さを学んだ。自分に与えられた役割を一人ひとりが
責任を持ってやったからこそできたと思う …K.M
・お互いのことを助け合うことで、理解しあい絆を深めることができた …K.I
・先生からのダメ出しがいっぱいで、はじめの頃はすごく嫌になってしまったけど、
「うまい!」と言ってもらえたときはすごくうれしくなりました …S.N
・本当に授業だけでは学ぶことができない経験ができたと思います …S.A
・一人ではできなくても仲間でやるとできるということを知りました …T.C
・いつも面倒なことは避けてきたけど、自分のできることを
探して動けるように変わった …K.F
・今までで一番頑張ったと思うくらいに頑張りました …F.K
・やっぱり「くやしい」っていうのが一番に思うこと …M.K
2. デザセンを通じて大事なことは…
デザセンを通じ、自ら学び、自ら能力を発揮する力を身に付けられることは重要ですが、一番の財産は人間関係の重要さ、協力、絆を学ぶことが一番大きいと思われます。これは、前述の生徒感想文からも明らかなことでしょう。難しい言葉で言うと「人間関係調整能力」とか言うそうですが、彼らが一番感じて成長した部分ではなかろうかと思われます。
私は、あくまで自主性を尊重する方針を貫いていますが、積極的でない生徒、休みがちな生徒をどう指導・助言していくかが教師の力量に問われてくるところだと思われます。私は生徒の貴重な夏休みや放課後などにおいて、集合日時・時刻、休日などこちらからは一切、強制しません。大会後の反省として、上位賞をとれなかった要因を100%まとまれなかったことに反省点を置いていることが多く、今後の課題となっています。
生徒には色々なタイプがいるので、適材適所に配置し実力を付けさせるのは監督である教師の仕事です。デザセンにおいては、教師の専門外においても学習面で生徒を引っぱっていく力が要求されますが、それよりも、この生徒の結束力及び人間関係調整に力を注ぐことの方が重要であり、成功するか否かはこの点にかかっているといっても過言ではないと思われます。その点、私の放任指導の未熟さが、自分のなかでは大きく反省材料となり、明日への課題となっています。
大阪市立淀商業高等学校
淀商業高等学校には、商業科と福祉ボランティア科が設置されています。また、商業科には安東先生ご担当の「コミュニケーション科学コース」のほか、3つのコース(会計科学コース、情報科学コース、流通科学コース)があります。
〒555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里3-3-15