DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL DESIGN|環境デザイン学科
環境デザイン学科
学生×教授対談 亀岡真彦(4年)×竹内昌義 准教授
- 竹内
- まず、亀岡君が何をやっているのか説明しくれますか。
- 亀岡
- 僕は地元である福島県福島市を対象敷地として卒業制作を行っています。僕の場合は福島という敷地は最初から決めていて、あとからテーマを考えました。まちから何かヒントを得ようと考え、小さな場所ということをキーワードにしようと思いました。
福島市の駅から少し離れた住宅地の中に小さな店舗が点在しています。その店たちはスペースが10畳とかそのくらいのスペースしかないのですが、何か人と人が密接に関わっているように思い、それらのような関係や現象を卒業制作で表せないかなと考えています。 - 竹内
- それは商店街みたいな感じですか?
- 亀岡
- 商店街というよりも、守られた場所というか、もっと人がずっとそこにいたくなるようなゆっくりした時間が流れているような場所です。
- 竹内
- 亀岡君は、授業とは別に、山形のまちで蔵プロジェクトとかをやっているじゃないですか。今話した事との関連があったら説明して。古いものに対するまなざし、そういう活動って、実際に新しいものを設計するのとは違うし、実際につくらないけど、関連はあると思うんだ。古いものを大事にしていって、そこにある空気みたいものを大事にすることでつくっていくものだと思うのだけれども、空気みたいな目に見えないなにかって、福島に関係あるように思うけど、どうですか?ある小ささって事を今回すごく強調しているじゃない?
- 亀岡
- 蔵プロジェクトをやっていて思うことは、ソフトを中心に提案、活動をしていて、何かそのソフトをうまく提案することで人と人の関係をつくっているということですね。その関係性みたいものが重要だと考えています。
- 竹内
- どういう関係?カメズバーみたいなもの(笑)?関係ない?全部、共通していると思うよカメズバーとも関係していそうだね。

- 亀岡
- カメズバーとは、自分の家でやっているバーのことなのですが、はじめは仲の良いメンバーで集まっていたのですが、次第に友達の友達とか、自分の友達、という友達ではなかった人が来るようになりました。そこで一緒にお酒を飲んだり料理を作ったりしていることが僕にとってすごく楽しい場所になっています。
- 竹内
- そういう空気ってなにで作れると思う?
- 亀岡
- それが小さな場所であり、家というプライベートな、守られた場所というのがその空気をつくっている要因の一つだと思います。蔵も同じことが言えると思っていて、山形の蔵は敷地の奥のほうにひっそりと建っていて、スケールが小さく、窓も小さい、守られたものだと言えると思います。1年目のオビハチのコンバージョンから始まり、今では複数の蔵がつながって山形にムーブメントを起こしています。その小さな密な関係がまちをつくっていくのではないかなと思います。
- 竹内
- 最近思うんだけど、ものとか、場所とか図面で表しにくいものだとおもうんだよ。亀岡くんのやっていることって、街の大きいスケールから町の小さいスケールをつくるまでやっていくんだけど、そういう空気感みたいなものをどこであらわしていくのかっていうのは、建物をつくるっていうのとまたちょっと違う話だと思う。でも表現しなくてはいけないから、工夫が必要だと思うよ。
- 亀岡
- そうですね、どう表現していったらいいのか悩みます。
- 竹内
- 例えば、中にあるインテリアの絵とか物とか、そういうもので表していくしかないよね。今、ここに模型があるけど、亀岡君はこうやって手を動かすと構築的というかカタイ印象があると思うんだ。
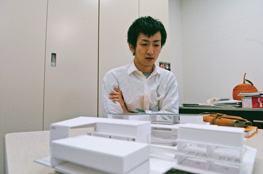
- 亀岡
- 以前言われたとき、確かにって思いました。
- 竹内
- その間をどう埋めていくかってことが、君の課題だと思うよ。
- 亀岡
- 自分は、0からつくりあげていくということが苦手というか、極端に言えばなんでもいい、ある場所があって、それをどういう良い場所にしていくのかということがすきなのかも知れません。
- 竹内
- そうはいっても、これからの卒業設計で、どう展開していくか楽しみにしています。がんばってほしいな。一回、俯瞰的にみて、街の中にこれだけのものがある程度必要なんだ、作った後に、もう一度、振り返って中に入った人がどうやってなにをしていくのか逆にもどしてくる作業こそが君の言っている小さいことをつくるのに必要なことだと思う。それはスケッチだったり、ものの絵だったりそういうなにか小さいことから形作っていくものだと思うんですよ。さきほどからの話は、単に建築というカテゴリーだけではなく、まちづくりとか、ひいては地球といった大きな環境まで巻き込む話で、その原点に、亀岡君のバーだったり、蔵だったり、そこから広がっていく環境というものがあると思います。

- ――
- 山形をテーマにすることは結構あるのですか?
- 竹内
- 授業の課題では、身近な場所をテーマに選ぶこともある。3年生の後半では、七日町を中心にしてどんなものを作ったらいいかという企画と、建物のデザインをします。端からみると、建物を建てる技術を学んでいるように見えるかもしれないけど、今本当に求められているのは技術だけではなくて「何を建てるのか」「どう変えるんだ」というビジョンや構成を考えられる力だと思います。そんな中で、蔵プロジェクトはすでにあるものを利用して何ができるか、古いものでも磨けば全く違う環境になる点で、その実習だと思います。何年か続けて活動をしているので『蔵プロジェクトです。』というと相談に来てくれる人もいるくらいになっています。ある程度の期間をやっているので、何か面白そうなことだというのは伝わっていると思います。
- 実際、街にいってどうしようかという提案をしたり、逆に依頼されるようなこともあります。若い人のアイディアが聞きたいとか、よく言われます。若い人のアイディアは新鮮だと思うので、卒業制作展にいらした方にはわかりにくい部分もあるかもしれません。建物やランドスケープの模型を通して、街や自然をどう変えたいのかやどう取り組むべきかという点を見ていただけたらわかりやすいと思います。いくつかのプロジェクトには、実際の山形の街を題材にしているのでそうした目で見てもらえるといいと思います。
- ――
- 他の4年生とジャンルをこえて言い合うことはありますか?
- 亀岡
- 自分だけだとかたまっていってしまうことがあります。やっぱり他の人の意見からヒントが出ることが多々あるので、聞くようにしています。

- 竹内
- 亀岡くんの持っている独特な視点はすごくいいんだけど、つくるとかたくなっちゃう。それをどう柔らかくしていけるのかが亀岡くんの課題です。例えば「日だまり」みたいな場所がいいなって言った時に、それをどうやって作るかという話。極端に言うと、大きさだったり、高さだったり、広さだったり囲まれ感だったり。亀岡くんの場合はもともとの考え方が強くあるので、それを実現するための手法を是非、卒業制作で獲得してほしいと思います。
- △このページのトップへ



